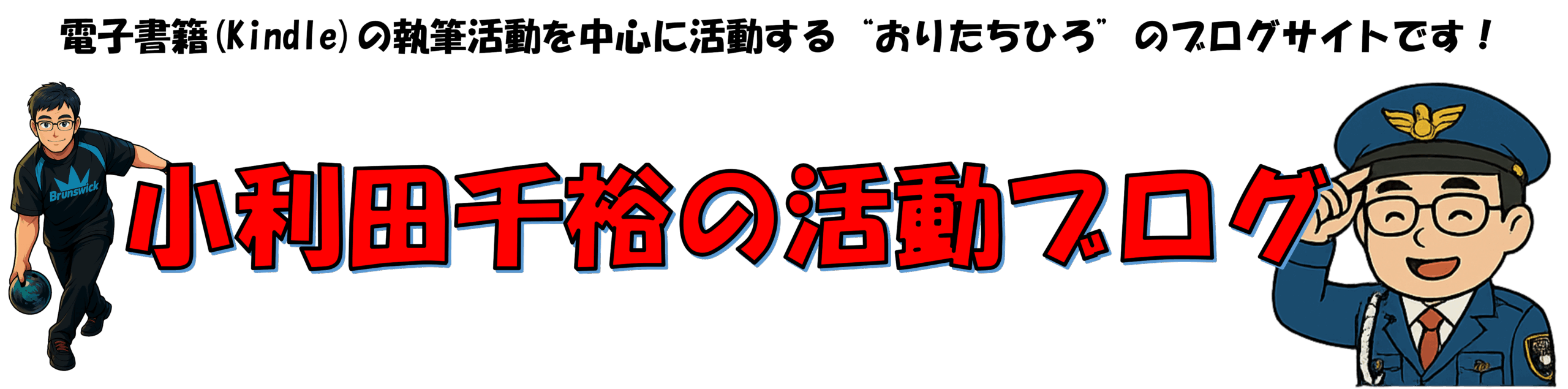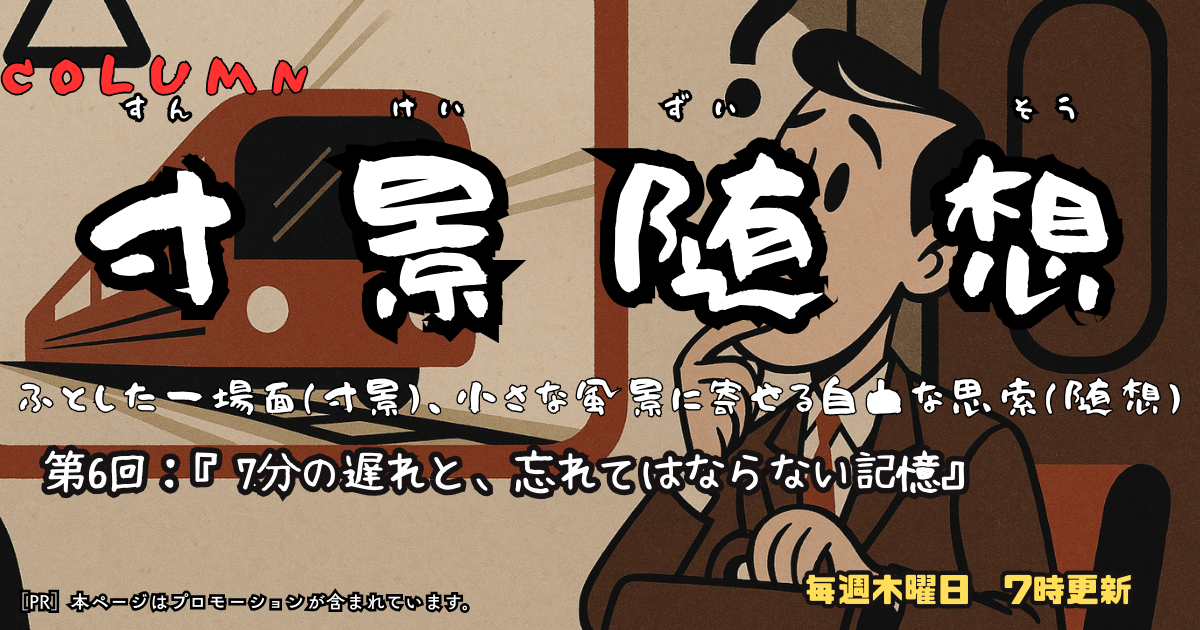朝の通勤電車に揺られる時間は、私にとって1日の始まりを支える小さな儀式のようなものだ。およそ40分、窓の外を流れる風景を眺めながら、今日も同じ時間に会社へと向かう。
ところが先日、その習慣にわずかな揺らぎが生じた。乗るはずの電車が7分遅れて発車したのである。私は当然、その分だけ会社への到着も遅れるだろうと考えた。だが実際には、到着時刻はいつもと変わらなかった。途中、車体がわずかに速く進んでいるように感じられたのは、気のせいではなかったのかもしれない。
そのとき私の胸に去来したのは、2005年4月、JR福知山線で発生した脱線事故の記憶だった。ダイヤの乱れを取り戻そうとした運転操作が、悲劇の一因となったと伝えられている。多くの命が失われたあの日以来、「遅れを急いで取り戻す」という行為の危うさを、私たちは忘れてはならないはずである。
公共交通機関において、最優先されるべきは安全である。7分の遅れは、仕事や予定の上では確かに小さくないかもしれない。しかし、それを取り戻そうと速度を上げ、万一の事故に繋がれば、その代償は計り知れない。失われた命は二度と戻らないのだから。
怖いのは、こうした「遅れを取り戻す」感覚が、鉄道会社にとっても乗客にとっても、慣習化してしまうことだ。急げば間に合うではないかという感覚が、やがて常態となり、危険を見過ごすことに繋がりかねない。
私たち乗客は、運転士と鉄道会社に命を預けている。その重みを忘れてはならない。7分の遅れを受け入れる心の余裕こそが、社会全体の安全を支える基盤なのではないだろうか。