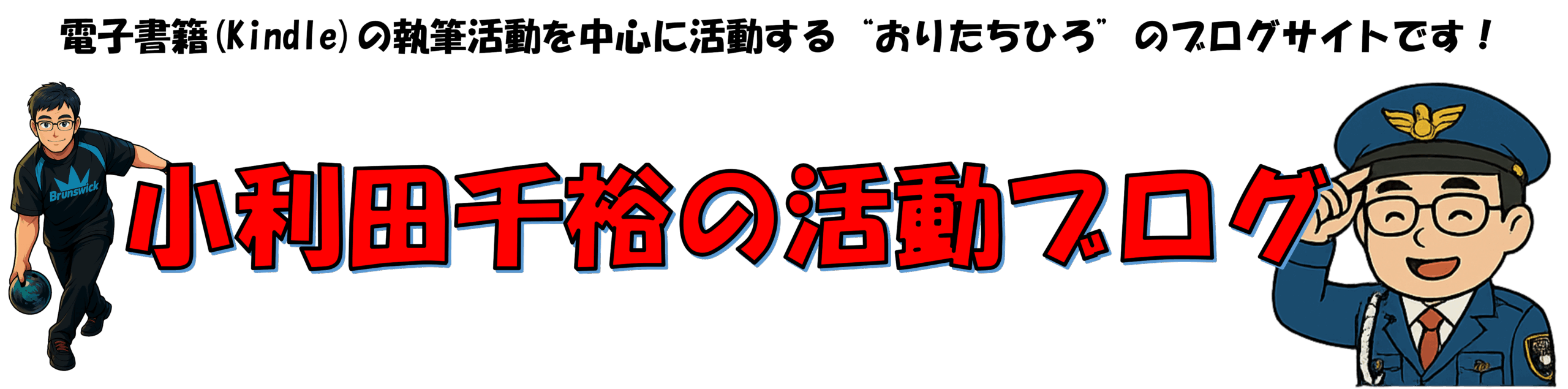先日、会社での飲み会のあと、最寄り駅からタクシーに乗った。夜の繁華街はそこそこ人通りがあり、飲食店も賑わっていた。普段と変わらぬ光景に見えたが、タクシー運転手の口から出た言葉は、思いがけず深い影を落としていた。
「今年の11月はおかしいくらいお客さんが少ないんですよ」
おどけた口調ではない。本気の“悲痛な訴え”そのものだった。
私はコロナ禍以降の変化が影響しているのかと尋ねたが、運転手は首を振った。
「いや、そうじゃないんです。お酒を飲んでタクシーに乗るお客さんは、ここ数年で一気に減ってしまって…」
確かに私が利用した居酒屋は満席で、二時間制の入れ替わりだった。客足が戻っていないようには見えない。だが運転手は言葉を続けた。
「若い人たちは飲まなくなりました。会社の飲み会にも来ない。誘ったらパワハラって言われる時代ですからね…」
その言葉に、私ははっとさせられた。
昔は会社の飲み会は“強制参加”に近かった。先輩の誘いを断ることはほぼ不可能で、断れたとしても二度目は許されない。楽しいことばかりではなく、むしろ上司の武勇伝に相槌を打ち続けるだけの退屈な時間も多かった。
しかし年齢を重ねるにつれ、酒の席には酒の席にしかない“距離の縮まり方”があることを知った。社内の肩書や立場をいったん外して話をすることで、相手の人柄が見え、理解が深まることがある。
もちろん無理強いすべきではない。だが、かつて当たり前に存在したコミュニケーションの場が、一つ、また一つと静かに消えていく寂しさも否定できなかった。
運転手の話は続く。
タクシー乗り場では以前より多くのタクシーが待機し、客を待つ列が途切れないという。
料金支払いの場面でも、かつては小さな“チップ”として小銭を渡す光景があったが、いまはQRコード決済が主流になり、チップ文化自体が消えつつある。
「小さな喜びすら減りましたよ…。まあ、時代なんでしょうけどね」
運転手は笑ってみせたが、その笑顔には苦味が混じっていた。
タクシーが街の動脈の一部である以上、その動きが鈍くなるということは、街そのものの活力が落ちているということでもある。
店は賑わっている。しかし街が元気であるかと言えば、別の話だ。
人が街に出ても、酒を控える。飲み会が減る。タクシーに乗らない。
つながっていないように見える現象が、静かに一つの線で結ばれている。
タクシーを降りるまでの短い時間、運転手の言葉は途切れなかった。
その“嘆き”は単なる景気の話ではなく、かつて街を彩っていた飲み会文化の衰退、そして人と人が交わる場が失われていくことへの痛みだったように思う。
街に再び賑わいが戻る日は来るのだろうか。
タクシーのライトが闇に消えていくのを見送りながら、私はふとそんなことを考えていた。