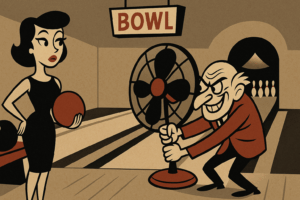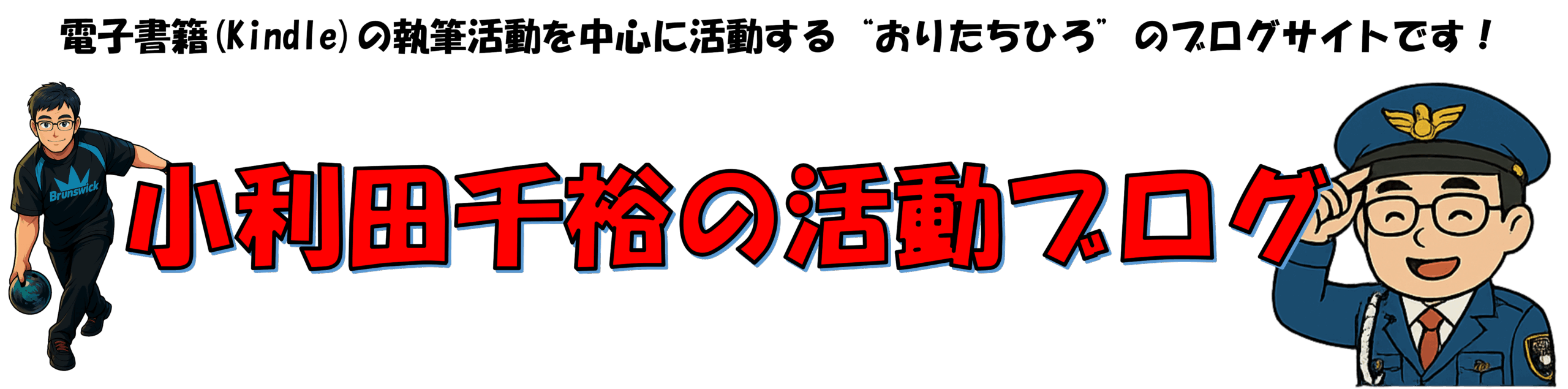夏の午後、ボウリング場の照明はいつもよりも鈍く見えた。冷房設備の不調により、天井から降りてくるはずの涼気は消え、空気は重たく、まるで熱を含んだ絨毯のように場内を覆っていた。
冷風機と扇風機が、いまや命綱のように稼働していた。私のチームの足元には、運営側が置いた一台の扇風機。練習ボールを終えた頃には、すでに額は汗で滲み、呼吸のリズムも浅くなる。そんな中で扇風機の風だけが、ささやかな慰めだった。
だが、その“風”は、ある瞬間に奪われた。
隣レーンにいた年配のボウラーが、無言のまま扇風機を持ち去ったのだ。理由も告げず、目も合わせず、自分たちの足元に2台を並べた。私たちの陣地には、ただ熱気だけが残った。
ボウリングという競技は、己との対話である。己のリズムを守り、仲間と互いに配慮しながら、ひとつの空間を共有する。だがそのとき私は、「配慮」という言葉がいかに脆く崩れやすいかを知った。誰かの快適が、誰かの不快によって成り立ってしまう瞬間がある。
齢を重ねた者は、若き日のように球を速くは投げられなくとも、思いやりの速さでは誰よりも先んじることができるはずだ。そう信じたい。だが、あの出来事は、私に問いを残した。
暑さの中でじっと立ち尽くす私たちに、誰も声をかけなかった。たった一台の扇風機をめぐる出来事は、単なる「小さなトラブル」ではない。見過ごされがちなこの場面にこそ、私たちの社会の一断面があるように思えてならない。
高齢化が進むこの国では、「譲られるべき人」が、「譲ることを忘れた人」になってしまうことがある。年を重ねるとは、鈍感になることではないはずだ。むしろ、目配りと気配りの繊細さこそが、真の年輪ではないか。
願わくば、私もまた、あのときの年配ボウラーのようにはなりたくない。
風を奪うのではなく、風を譲る人でありたいと、心から思った夏の日だった。